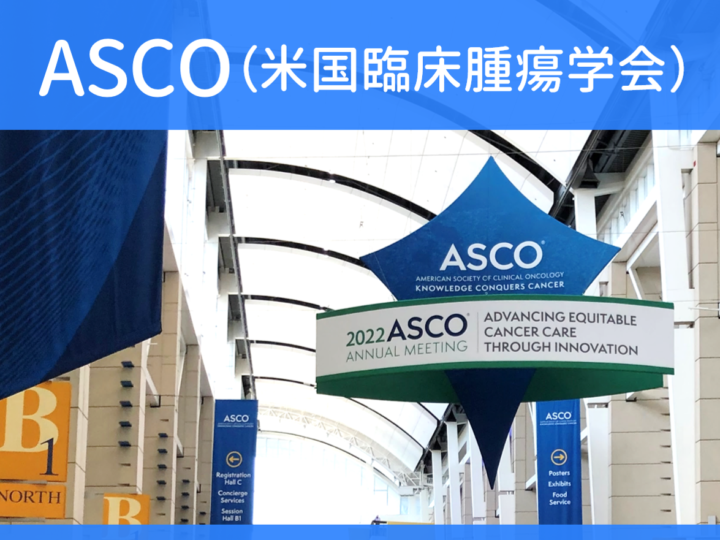胸部がんとメラノーマの抗PD-1療法著効と分子レベルの転帰予測【ASCO20】
ジョンズホプキンス大学キンメルがんセンターの胸部がん専門家およびがんゲノム専門家は、がん治療・ケアに携わる医師および専門家が所属する国際学会である米国臨床腫瘍学会(ASCO)の年次総会で、中皮腫、肺がん、および悪性黒色腫に関する有望な知見および研究を新たに報告した。今年度の発表者には、ASCO Young Investigator賞およびMerit賞を受賞した2名が含まれる。本総会は、5月29~31日にバーチャル会議として開催された。
以下のプレゼンテーションが発表された:
–中皮腫に対する一次治療として、化学療法と免疫療法デュルバルマブを併用
PrE0505臨床試験は、切除不能な悪性胸膜中皮腫(アスベスト曝露に起因することが多く、肺の表面を覆う胸膜に発生し治療が難しい希少がん)に対する免疫療法と化学療法の併用療法の有効性を評価した。本研究は、腫瘍学准教授、キンメルがんセンター胸部がん臨床研究プログラムディレクター、およびブルームバーグ・キンメルがん免疫療法研究所の研究者であるPatrick Forde医学学士によって発表され、全米の15のがんセンターにて登録された55人の患者が、一次治療として抗PD-L1抗体薬デュルバルマブ(販売名:イミフィンジ、AstraZeneca社)と化学療法シスプラチン+ペメトレキセドの併用療法を受けた。
患者は、3週間毎に6回の併用療法の後、最長1年間、免疫療法剤デュルバルマブの投与を受けた。化学療法単独ではこれまで12カ月とされた全生存期間が、化学療法と免疫療法併用療法によって20.4カ月に延長した。切除不能な中皮腫患者の生存期間が20カ月を超えたのは、本試験が初めてである。治療は全体的に良好な忍容性を示し、予期せぬ有害事象は報告されなかった。
「炎症は胸膜中皮腫の発症の鍵を握り、免疫療法の重要な標的となっています。さらに、先行研究において、前治療歴のある患者に対する抗PD-1抗体薬治療が有望な結果を示唆したことから、今回の併用療法試験を行うことになりました」とForde医学学士は述べる。「未治療の切除不能な悪性胸膜中皮腫患者に対するデュルバルマブと標準化学療法の併用は、有望な全生存期間中央値を示唆しています。現在、この併用療法の有効性を検証する第3相試験の準備を行っています」。この第3相試験は、DREAM3R試験として、2020年後半に米国とオーストラリアで開始される予定である。
腫瘍学教授およびブルームバーグ・キンメルがん免疫療法研究所の上気道消化管部門共同ディレクターであるJulie Brahmer医師と、ジョンズホプキンス大学医学部腫瘍学助教授および胸部がんバイオバンク・ディレクターであるValsamo Anagnostou医学博士を含む研究者らは、患者45人の腫瘍組織検体を用いて、遺伝子発現解析および免疫細胞レパトア解析を行った。PD-L1発現および腫瘍遺伝子変異量(腫瘍細胞中の遺伝子変量を示す指標)は、いずれも免疫療法に対する治療応答性を予測するバイオマーカーまたは指標として使用されている。しかし、本研究において、PD-L1発現または腫瘍遺伝子変異量のいずれにも、治療応答性との関連は認められなかった。より精密な遺伝子発現、および遺伝子機能解析が、治療応答性/耐性に関する分子機構を解明していくだろう。
病理医の顕微鏡には、PD-L1が武装し、免疫システムからがん細胞を守っているように映る。デュルバルマブを含む免疫チェックポイント阻害剤と呼ばれる免疫療法は、PD-L1シグナルを自らの生存のために利用しているがん細胞の働きを妨げ、免疫細胞による認識と攻撃から逃れられなくする作用を有する。
関連演題のポスター発表:
Joshua Reuss医師(ジョンズホプキンス大学キンメルがんセンターの腫瘍学フェロー)は、進行中のNeoMeso臨床試験の最新データを発表した。本試験では、予後改善を目的として、切除可能な胸膜中皮腫患者に対する術前チェックポイント阻害剤投与の安全性と有効性を評価した。現在、化学療法、手術、放射線療法といった積極的な治療を行っても、ほとんどの患者は再発して死に至ってしまう、とReuss医師は語る。
「転移性胸膜中皮腫に対する免疫チェックポイント阻害剤の作用機序を解明するとともに、限局性胸膜中皮腫に対する最適な治療戦略を確立することは、緊急を要する課題である」とReuss医師は述べる。
ステージ1~3の胸膜中皮腫と診断された患者は、手術前に免疫チェックポイント阻害剤ニボルマブ投与を3回受ける。もう一つの患者群では、ニボルマブ(販売名:オプジーボ、Bristol-Myers Squibb Co.社)およびイピリムマブ(販売名:ヤーボイ、Bristol-Myers Squibb Co.社)チェックポイント阻害薬2剤による併用療法を評価する。手術後に一部の患者は化学療法や放射線治療を受ける。また、最長1年間、ニボルマブによる維持療法を受ける。
その他の研究チームメンバー: Valsamo Anagnostou, M.D., Ph.D.; Kellie Smith, Ph.D.; Janis Taube, M.D., M.Sc.; Gary Rosner, Sc.D.; Khinh Ranh Voong, M.D., M.P.H.; Russell Hales, M.D.; Stephen Yang, M.D.; Richard Battafarano, M.D., Ph.D.; Patrick Forde, M.B.B.Ch.
Jarushka Naidoo医学学士は、肺がん免疫療法の副作用管理における第一人者であり、非小細胞肺がん患者における、抗PD-L1抗体薬デュルバルマブの副作用に関する知見を発表した。
–がん細胞と免疫細胞の間のクロストークから免疫療法への反応を読み解く
より優れた免疫療法に対する治療応答性予測バイオマーカーが求められている。研究者らは、免疫チェックポイント阻害剤による治療中にがん細胞と免疫細胞の間で複雑な細胞間コミュニケーションが起こることから、細胞間のクロストークを解明することが、免疫療法に対する治療応答性が高い可能性のあるがんの特定につながるのではないかと考えている。腫瘍学助教、胸部がんバイオバンク・ディレクター、およびブルームバーグ・キンメルがん免疫療法研究所の研究者であるValsamo Anagnostou医学博士と研究者らは、腫瘍と免疫システムの相互作用を解明するために機械学習またはAI(人工知能)を用いて、がん細胞および免疫T細胞由来の遺伝子、およびトランスクリプトーム/RNAを包括的に解析した。研究者らは、免疫療法に対する治療応答性が高い患者を内科医が層別化することを可能とする、統合的な分子バイオマーカーを開発することを目指している。
研究者らは、チェックポイント阻害剤ニボルマブ単独投与、またはニボルマブともう一つのチェックポイント阻害剤イピリムマブとの併用投与を受けた進行性メラノーマ患者64人の組織検体を分析した。チェックポイント機構は、体が持つ免疫システムのアクセルとしての「Go」、ブレーキとしての「Stop」信号を出して、免疫システムの活性化と抑制を制御する。がん細胞は、免疫システムから身を隠し攻撃を避けるためにこれらのチェックポイント機構を利用しているが、チェックポイント阻害剤はこの機構をがん細胞が利用できないようにし、免疫システムががん細胞を認識できるようにする。
高い腫瘍遺伝子変異量(腫瘍組織中の遺伝子変量を示す指標)は、免疫療法の治療応答性予測および予後予測に使用される新しいバイオマーカーであるが、限界があり、本研究では治療応答性との関連を明らかにすることはできなかった。腫瘍組織内における、がん細胞を検出し破壊する能力を持つT細胞の増加、T細胞集団の変化、およびがん細胞に侵略者として目印をつける抗体を産生するB細胞の存在が、チェックポイント阻害剤を用いた免疫療法の重要な治療応答性予測因子であった。
研究者らは、がん遺伝子、T細胞およびB細胞の特徴を組み合わせてリスクスコアを作成し、患者を高リスク群と低リスク群に層別化した。その結果、高リスクを示した患者はチェックポイント阻害剤による奏効可能性が低いことが示された。このリスクスコアは、既存の免疫療法に対する治療応答性予測バイオマーカーである腫瘍遺伝子変異量および腫瘍中のPD-L1発現を上回る性能を示した。
「分子的特徴を組み合わせた統合的アプローチは、チェックポイント阻害薬による免疫療法に反応する患者の予測において有望だと考えられます」とAnagnostou医学博士は述べる。「これらの知見は、腫瘍と免疫システムの間に多様な相互作用が起こっていて、臨床反応を高めるために既存のT細胞およびB細胞による免疫の働きが重要な役割を果たすことを明示しています」。さらなる研究が現在も進行中である。
これらの知見についてのビデオ
その他の研究チームメンバー:Daniel Bruhm, B.S., Noushin Niknafs, Ph.D.; James White, Ph.D.; Toni Ribas, M.D.; Suzanne Topalian, M.D.; Drew Pardoll, M.D., Ph.D.; Victor Velculescu, M.D., Ph.D.
–非小細胞肺がんに対する、非侵襲的な免疫療法への治療応答性予測
一次治療における免疫療法、および免疫療法/化学療法の併用は、進行性非小細胞肺がん患者に対する治療法として承認されているが、従来の画像検査による治療応答性診断は容易ではない。ポスター発表の中で、腫瘍学のフェローであり、2020年にASCO Young Investigator AwardとMerit Awardを受賞したJoe Murray医学博士は、血液中に放出されるDNAを分析する非侵襲的な検査法であるリキッドバイオプシーが治療応答性を正確かつ迅速に予測できる可能性があると言う。
研究者らは、治療応答性の測定性能を向上するため、血中循環がんDNA(ctDNA)(血中に放出されるがんDNA)の検証を行っている。腫瘍由来の循環DNAは、高い重複度での塩基配列解析(ディープシークエンシング)および血球由来のDNA変異を除去することによって非常に慎重に検出された。
Murray医師は、「臨床における意思決定の支援では、治療中に起こる治療応答性を正確に評価できる必要があります」と述べ、「治療応答性モニタリングに使用されるゴールドスタンダードであるCTスキャンなどの画像検査では、免疫応答を正確に検出できない可能性があります」と付け加えている。
非小細胞肺癌に対する免疫療法を受けた31人の患者から採取された143の血漿検体と24の白血球検体を解析した研究では、PD-L1発現と関係なく、ctDNAは臨床転帰を予測した。さらに、ctDNAが治療応答性を早期に検出したことから、臨床転帰の改善を目的とする治療の意思決定において、ctDNAがより優れた指標となる可能性があるという。
その他の研究チームメンバー:Kristen Marrone, M.D.; Jarushka Naidoo, M.B.B.Ch.; Benjamin Levy, M.D.; Christine Hann, M.D., Ph.D.; Josephine Feliciano, M.D.; David Ettinger, M.D.; Julie Brahmer, M.D.; Patrick Forde, M.B.B.Ch.; Victor Velculescu, M.D., Ph.D.; Valsamo Anagnostou, M.D., Ph.D.
Erica Nakajima医師(腫瘍学フェロー)は、2020年ASCO Young Investigator賞を受賞し、早期非小細胞肺がんに対する術前免疫療法において、CTおよびPET画像の特徴と治療応答性との関連について、ポスター発表による報告をした。
その他の研究チームメンバー:Patrick Forde, M.B.B.Ch.; Martin Pomper, M.D., Ph.D
原文掲載日
【免責事項】
当サイトの記事は情報提供を目的として掲載しています。
翻訳内容や治療を特定の人に推奨または保証するものではありません。
ボランティア翻訳ならびに自動翻訳による誤訳により発生した結果について一切責任はとれません。
ご自身の疾患に適用されるかどうかは必ず主治医にご相談ください。
皮膚がんに関連する記事
米FDAが転移/局所進行皮膚扁平上皮がんにcosibelimab-ipdlを承認
2025年2月1日
メラノーマ予測ツールにより免疫療法薬の選択が可能に
2024年12月9日
ニボ+イピ併用で転移メラノーマの長期生存は劇的に改善
2024年10月22日
【ASCO2024年次総会】メラノーマ:術前のニボルマブ+イピリムマブが術後療法単独より転帰を改善
2024年6月24日